Who We Are
Strategy
エプソンの事業戦略を語る
ニューノーマル時代の社会課題解決へ。エプソンDXの今、未来
ものづくりに付加価値を。DXを通じ、エプソンの事業成長を牽引する
DX推進本部 副本部長/菅原 文昭
エプソンは重点テーマの一つに「DX」を掲げています。強い製品群を抱えるエプソンに今なぜDXが求められるのか、その背景や狙いをお聞かせください。
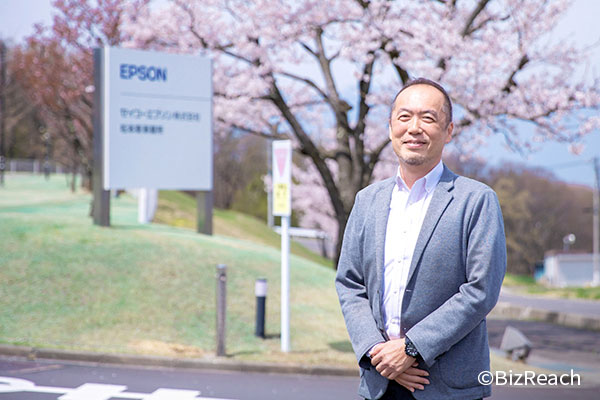
テクノロジーの進化が激しい今の時代において、私たち製造業が手掛ける事業はもはや、「ものをつくる」だけに留まりません。ものづくりを土台とし、そのうえでどういった付加価値を提供できるかが重要な事業戦略になっています。そして、付加価値を生み出すためには顧客ニーズの見極めが欠かせません。この見極めに必要なものは何か――。それを突き詰めると、DXに帰結するのです。つまりDXは、製品にプラスアルファの価値を生み出す重要不可欠な手段の一つなのです。
エプソンでは、従来からさまざまなテクノロジーを取り入れ、積極的にデジタル化に取り組んできました。ただそれらは、まだ個別最適の状態にあります。今後はDX推進本部が中核を担い、各事業部や本部、さらには国内外の関連会社とも連携を強化しながら全社横断での本質的なDXを推進していきます。
具体的にどのようなDXを推進されていますか。
私たちが推進するDXは、社内視点と顧客視点の大きく2つに分けられます。まず、社内視点としては「コーポレート・トランスフォーメーション」を掲げています。事業に直接貢献するDXをキーワードに、事業部間の連携やコミュニケーション強化による組織力の向上を推進しています。
一方、顧客視点として掲げるのは「カスタマーエクスペリエンスの向上」であり、エプソンの価値をいかに広げ、伝えていくかが重要なポイントです。テクノロジーの活用はもちろん、環境に配慮したものづくりというエプソンならではの取り組みを対外的により積極的に発信していきます。これが、「持続可能でこころ豊かな社会の実現」を目指すエプソンのDXの在り方です。
組織とカルチャーをも変革し得る、プロアクティブな人材を求む
そうしたビジョンを達成するにあたり、現状のエプソンのDXをどう捉えていますか。良い点と課題の両面を教えてください。

前述のとおり、エプソンにはすでにDXに必要なテクノロジーがほぼ網羅されています。これは良い点と言えるでしょう。課題はそれらが点で存在していることであり、面として機能していない点にあります。技術的な問題ではなく、それを使いこなす組織や文化的な問題が大きいと考えています。
そのため、今はまずDX組織を整え、カルチャーをつくっていく段階にあると捉えています。現場すなわち事業部側と、私たちDX推進本部が連携を強め、同じ方向を向き、共通の価値観を持つことが大切です。それが、全社最適のDXを実現するカギとなります。そうした組織づくりをリードできる人材こそ、今のエプソンには必要です。
DXをリードする人材を募集されるとのことですが、どんな人に仲間になって欲しいですか。
技術力や最新テクノロジーへの知見はもちろん重要ですが、どちらかというと周囲を巻き込み、自ら考えて行動に移せるプロアクティブな方を求めています。具体的には、自らも事業側の一員として課題を可視化し、同時に全社に目を配りながら最適なDXを組み立てていける方ですね。
またDXの実現には、役職や立場に関係なく、それぞれが持つスキルや得意なことを発揮しながら、スピーディーに業務を推進していく必要があります。ある種の遊び心を持ちながら軽やかに、時には起爆剤のように、エプソンに新しいカルチャーをもたらしてくれる方に仲間になって欲しいと思っています。
エプソン社員の自社製品・ブランドへの情熱が、転職の決め手に
次に、菅原さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
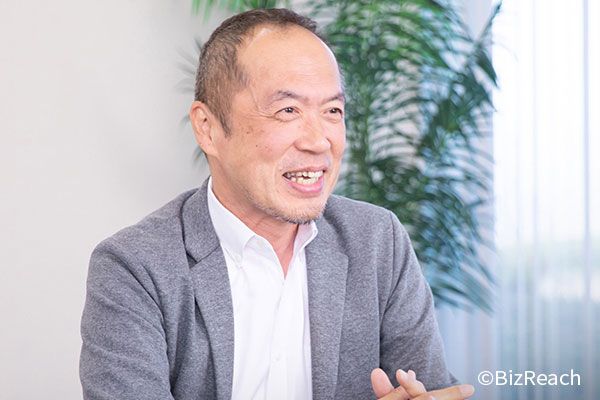
私は1987年にシステムエンジニアとしてのキャリアをスタートし、米国系通信事業会社の日本法人に在籍していた時にセキュリティ領域に携わるようになりました。当時は日本初の商用プロバイダーが提供され始めたころで、初めてインターネットに触れた時には大きな衝撃がありましたね。インターネットとセキュリティは切っても切り離せない関係だと確信し、セキュリティセンターやデータセンターの立ち上げ、マネージドセキュリティサービス業務などを経験しました。
そのなかで「セキュリティ領域を軸に通信以外にも知見を広げたい」という思いが芽生えたのをきっかけに、コンサルティング企業に転職しました。お客様企業にセキュリティを提供する側になり、大きな責任を感じると同時に、自分の言葉が価値となって対価をいただくコンサルティングという仕事の面白さを体感しました。お客様から信頼されることが嬉しかったですし、お客様に応えるために学び続ける大切さも知りました。
その後は外資系のコンサルティング企業に転職し、いかに自分を売り込むかというビジネススキル、全社組織と戦略のなかで立ち位置を確立するバランス感覚、経営層と関係性を深めるコミュニケーション力などさまざまな学びを得ました。そんな折にエプソンから声がかかり、現職に至ります。
今こそ変革の時。豊富なテクノロジーを点から面へと進化させる
エプソンには2023年に入社されていますね。転職の決め手は何でしたか。

長年コンサルタントとして働くなかで、「もし次に転職するのならば、自ら手を動かしながら事業に貢献したい」と事業会社で働くことを考えていましたし、また国を代表する日本企業で働きたいとも思っていました。エプソンは、まさに私が働きたいと思っていた会社の一つだったのです。
入社の決め手は、エプソンという会社に対する社員の情熱です。初めてエプソンのCIO(最高情報責任者)と話した時に、自社やそのブランドに対する愛や思いをとても強く感じました。また、良い部分だけではなく、エプソンをさらに良くするために変えていかなければならない部分についても明確に伝わってきました。その情熱に惹かれ、エプソンに新たな変化をもたらす、その一員として貢献したいという思いで入社しました。
エプソンに今入社することに、どのようなメリットがあると思いますか。
DX推進本部のカルチャーとして、職種やレイヤーで業務を区切りすぎることなく、自薦他薦問わず手を挙げた人に仕事を任せることを大切にしています。テクノロジーの世界は日進月歩で変化が激しい領域です。技術の陳腐化が早いため、大切にしていることはやりたいという意志です。新しいことにどうせチャレンジするのなら、意志ある方にどんどんお任せしたいと思っています。「やりたい人がやる」こんな組織をつくりたいですね。一方、ご自身の意思と考えを持って行動することが難しい方には、やりにくさを感じる職場かもしれません。
そしてゆくゆくは、こうした柔軟でプロアクティブな組織カルチャーを全社に広げていきたいと私は思っています。変革期にあるエプソンの組織づくりを牽引するというのは、今しかできない貴重な経験だと言えるでしょう。
長野から世界へ。分散型社会を体現するエプソンで働く魅力
続いて「長野で働く」ことについて伺います。菅原さんはエプソン入社を機に長野県に転居されていますが、生活はいかがですか。

私はキャンプが好きで、以前からよく長野県を訪れていたので、今の生活にもとても満足しています。転居についても、「長野に住んだら30分でキャンプ場に行ける」とむしろメリットを感じていて、躊躇なく飛び込みました。
毎朝玄関を出ると目の前に壮大な北アルプスが広がっていて、日常的に大自然を感じています。東京での生活と比べると明らかにストレスを感じる時間が減ったかもしれません。それに伴って生活スタイルも自然と変化し、最近では朝早くにオフィスに行き、一人でじっくりと考え事をする時間を持つようになりました。非常に生産的で有効な時間の使い方ができています。
唯一心配していたのは生活の利便性でしょうか。東京で生活していた時には徒歩数分でスーパーやコンビニに行けたのに対し、今では週末に車で買い物に出かけ、そのついでに気になっていた店でランチを楽しんでいます。ただ、慣れてしまうと不便を感じることはなく、生活面での不安はすぐに払拭されました。
長野というローカルな地から、グローバル規模の仕事を手掛ける醍醐味は何でしょうか。
エプソンのDNAである「省・小・精の技術」を受け継いだエプソンの製品やサービスを通して世界中のお客様とつながる、それがエプソンのDXです。今の時代、東京にいないとできない仕事はありません。どこにいてもグローバルな仕事ができる、まさに「長野から世界へ」、こうしたユニークな企業でDXを推進するというのは、ほかではなかなか得られない経験ではないでしょうか。
終わりのないDXを追求する「好奇心」こそ、未来を切り開くカギとなる
最後に、記事の読者へのメッセージをお願いします。

テクノロジーが急速に進化している今、ほぼすべての企業で大なり小なりDXが行われています。そのなかで重要なのは「何のためにDXが必要なのか」という目的をしっかり据えること。企業ごとの違いはこの目的に表れ、将来の企業と事業の強みとなっていくでしょう。
テクノロジーの進化、人の進化とともに、DXも進化する必要性があります。そうしたDXを推進する私たちに求められるのは、固定観念にとらわれず、常に変化を受け入れ柔軟に対応していく力だと言えます。
そしてキャリアを築くうえで最も大切なのは、「好奇心」だと思います。私自身の経験としては、何か物事を追求する根源には必ず好奇心がありました。エプソンの強みである「省・小・精の技術」から生み出す価値を社会課題解決につなげていく、そのDXに強い好奇心を持って邁進してくれる仲間をお待ちしています。
